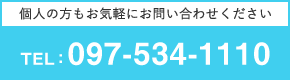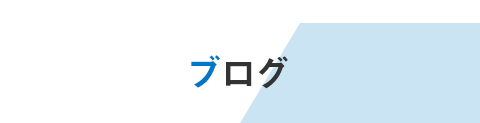知られざる消火器のルーツ
コラム
私たちの身近にある消火器。
火災時に初期消火を行うための重要な消防設備として、学校やオフィス、公共施設などさまざまな場所に設置されています。
しかし、その「当たり前」の存在には、長い歴史と多くの工夫が積み重ねられています。
◇消火器の始まり
消火器の起源は約300年前のヨーロッパにさかのぼります。
最初の消火器は1723年、ドイツ出身のアンブローズ・ゴッドフリーが発明しましたが、火薬を使う仕組みで実用性に乏しく普及しませんでした。
その後、19世紀初頭にイギリスのジョージ・ウィリアム・マンバイが圧縮空気で炭酸カリウムを噴射する携帯型消火器を開発し、現代の消火器の原型となりました。
◇日本での消火器の普及
日本では江戸時代に町民による「火消し文化」がありましたが、装置としての消火器が導入されたのは明治時代です。
明治20年代にドイツ製の硫曹式消火器が注目され、1895年に丸山商会が国産消火器の製造・販売を開始。
さらに1918年には泡消火器が開発され、1951年には粉末消火器が輸入されました。
こうして日本でも消火器は改良され、軽量で扱いやすい国産品が普及したのです。
株式会社武田商会は大分市を拠点に、大分県全域で火災受信機や誘導灯の設置、消防設備の保守・点検を行っています。
消火器の販売や処分代行にも対応しており、ご自宅向けのおしゃれなデザイン消火器も取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問合せはこちら https://www.k-takeda-syoukai.com/contact/